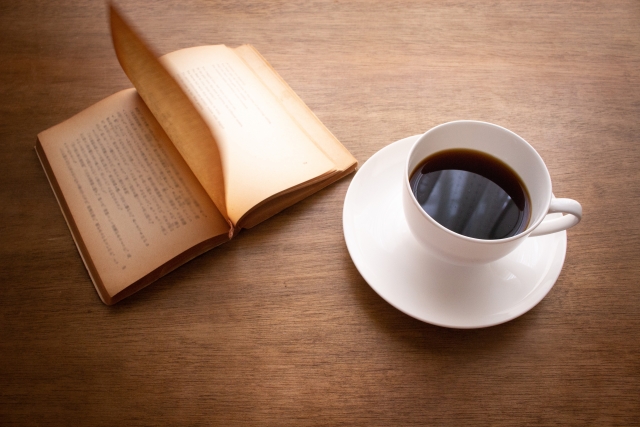料理評論家って、どんな人?
2018年11月7日

近年、料理研究家と呼ばれる人が料理番組に登場しますが、似たような肩書きで料理評論家という人を見かけることはありませんか?日本や海外で少しずつ増えつつある料理評論家ですが、どんな仕事をしている人なのか、あまり知られていないのではないでしょうか。
今回は、料理評論家はどのような仕事をしているのか、料理評論家にはどうすればなれるのかなどについて、お伝えします。
料理評論家とは?
料理評論家という仕事には、明確な定義がありません。それこそ、本人が明日から「料理評論家になる!」と決断してしまえば、事前に資格を取得したり、特定の組織に属さなくても料理評論家になることはできます。
昔から評論家は、物事を分析し、評論する人として、多くの分野で活躍してきました。大学教授や学者が専門分野を生かして評論することが多く、常に自分の意見を述べることが求められます。
そのため、料理評論家になるには、下記のような素養が最低限必要です。
- ◆料理に関する圧倒的な知識量
- ◆料理人の意図を読み取る仮説検証力
- ◆味を楽しむ舌や眼
- ◆料理の本質を見極める洞察力
- ◆感じたものを表現し、伝える力
料理評論家は、メディアを通じて情報発信することで、自らの価値を提供するため、料理について誰よりも知っている必要があります。そのためには、日々、膨大な情報をインプットし、料理人が作り上げたレシピを深く掘り下げる探究心や研究心が必要です。
料理評論家の仕事は、無限大
料理評論家として働くには、社会から認知され、一定の評価を得る必要があります。そのためには、多数の料理本を出版したり、テレビ番組に出演して知名度を上げたり、セミナーを開催するなど、さまざまな方面で「努力」していくことになります。
なお、料理評論家として社会に認知されると、次のような仕事へのオファーがあるかもしれません。
- ◆料理雑誌のコラムの執筆
- ◆料理番組の出演依頼
- ◆料理の評論本の執筆
- ◆セミナー講師としての出演依頼
そのため、料理評論家として一定の人気さえ出てくれば、多くのフィールドで活躍できます。そのためには、日頃から記事を書くためのライティング能力やテレビ番組や公演で分かりやすく話すための話術を、磨いておくと良いでしょう。
料理評論家になる方法
インターネットが発達した現代は、料理評論家として活躍しやすい環境が整っていると感じます。なぜなら、ブログやSNSなど、数多くの情報発信ツールがすでに整備されているからです。本気で料理評論家を目指すなら、次のようなことから始めてみてはどうでしょうか?
- ◆日々、食べ歩いた料理に関する情報をSNSやブログで情報発信する。
- ◆料理雑誌で気になったものがあれば、周囲に紹介する。
- ◆話題になりそうな料理を発見したら動画を撮影し、動画サイトへアップする。
このような活動を少しずつ続けていれば、いずれ多くの人に興味をもってもらえるかもしれません。良い編集者などに巡り合うことができれば、「コラムを1本書いてもらえませんか?」と、仕事につながるような話も、できるようになるでしょう。
将来、コラムの執筆から、テレビ出演の依頼が入り、料理評論家として働ける可能性も十分にあります。目標を高く掲げ、自分ならではの「強み」や「個性」を確立して、積極的にPRしていきましょう。
もし、料理評論家を目指しており、料理を基礎から本気で学びたいと感じているのなら、私の通う京都調理師専門学校で専門的な調理技術や、料理の歴史、料理に使う道具の知識や使い方など、料理に関するさまざまなことを、深くを学んでみませんか?京都調理師専門学校では、「ほんまもんの技」と「おもてなしの心」を学ぶため、3つの学生レストランを併設しています。2018年4月には、新キャンパスも開設され、最新の施設設備の中で学ぶ環境が整っています。
他にも、専攻するコースによって、和食やイタリアン、フランス料理まで、世界中の料理の歴史や文化、マナー、伝統的な調理技法が学べる体制が整っています。料理について深く学びたい方は大歓迎です。